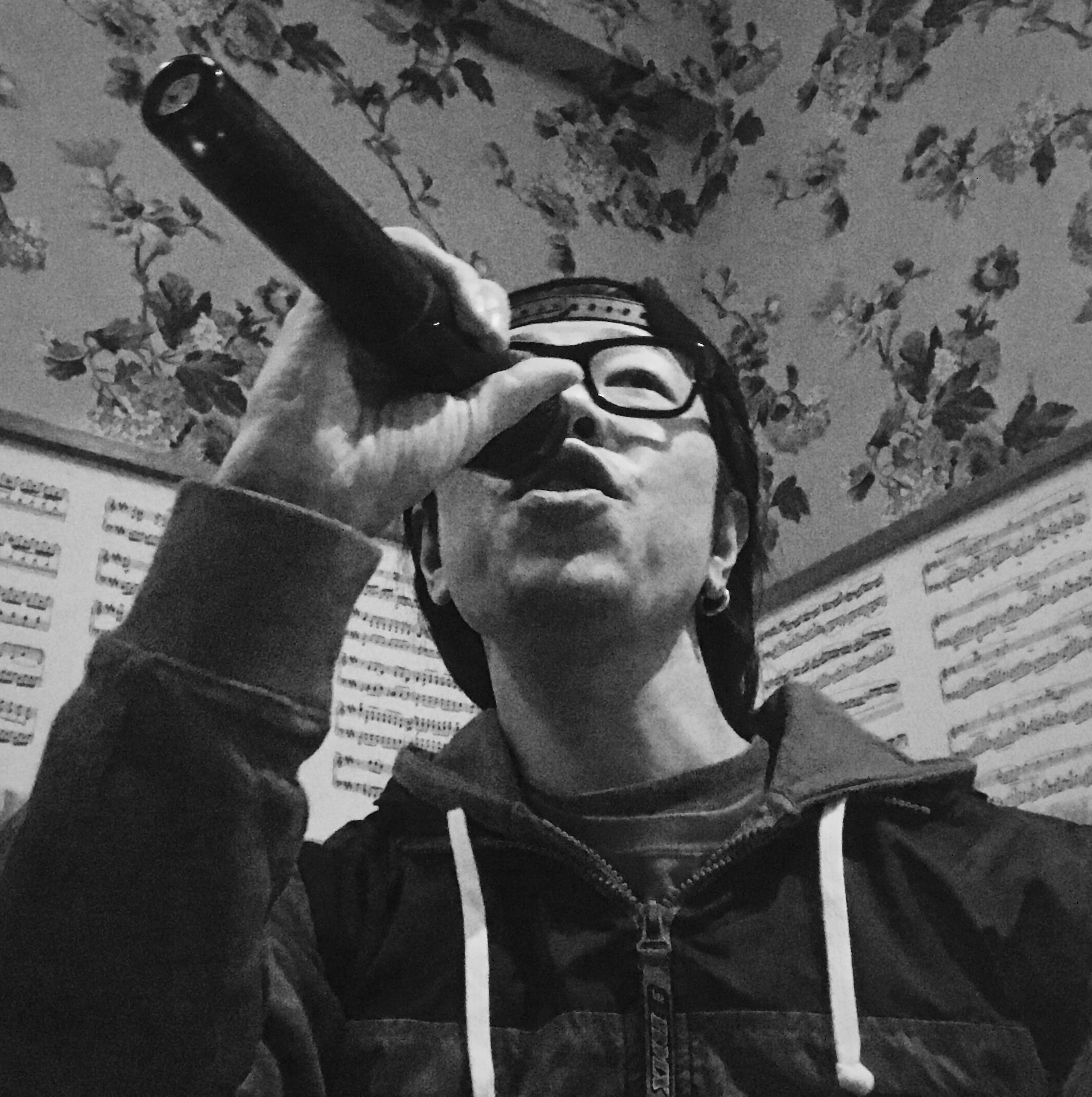前回からのつづき
ちなみに、手を叩くこと、踊ること、も歌うことと同じくらい好きであっていただけると、すごく良いです。
音楽を楽しむにあたって。
音楽と仲良くなりたかったら、一人部屋で音楽をかけて、一緒に歌って、手を叩いて、身体を動かしてみてください。
恥ずかしい?バカみたい?
できないですか?誰も見てなくても?
もしそういう方がいらっしゃったら、自分はよっぽど音楽を楽しみにくい性格なんだ、と思ってください。
やりたいことがサックスでも、ギターでも、ピアノでも、なんだったとしても、この部分ができないまま、わからないままでは、その先に待っているのは見た目だけの、ポーズだけの、表面だけの音楽だと思ってください。
「リトミック」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
一般的には幼児に向けた「身体を使って音楽の楽しさを感じる」ためのプログラムです。
私が常々、不思議に思っているのは、なぜリトミックは小さな子供しかやらないのか、ということです。
大人がやってはいけないんですかね?
もちろん、一般的な幼児向けのプログラムを大人がやるのは抵抗があると思いますが、その効果は大人にも、いや、むしろ大人にこそあるのではないでしょうか。
音楽に合わせて、たくさん身体を動かし、リズムに合わせて手拍子をし、大きな声で歌う。
音楽を始めようと思ったときの、カッコイイ、素敵なイメージとはかなりギャップがあるかもしれませんが、まず最初にこれを、恥ずかしがらずに、煩わしがらずに、やっていただきたいと思っています。
そうすることで、固い身体がほぐされ、発することや表現することのシンプルな喜びを感じられ、リズムの感覚、メロディの感覚、ハーモニーの感覚の礎が作られます。
逆に、それらがない状態で楽器の練習に入ってしまうと、楽譜通りに正確に運動しなければ、という硬い発想、思うように動かない固い身体、感じられないリズム、メロディ、ハーモニー……。楽しむ、からは程遠いです。
当スクールでは、すべてのコースにおいて大人のためのリトミックを含んだレッスンを実施していきます。
と若干の宣伝を挟んだところで、
写真は、スクールのバルコニーからの景色です。