何かやるべきことがあっても、いや、あるときこそ、ミョーに見てしまうYoutube。
危険ですね。
そんな危険を犯して今日見たのは、ビジーフォー。
グッチ裕三さんとモト冬樹さんの。
なぜかYoutubeにおすすめされていたのです。なぜ?
その昔は苦手だったんですよ。どこがって言えないけど、なんか。
今見たら……けっこう感動しました。
何かやるべきことがあっても、いや、あるときこそ、ミョーに見てしまうYoutube。
危険ですね。
そんな危険を犯して今日見たのは、ビジーフォー。
グッチ裕三さんとモト冬樹さんの。
なぜかYoutubeにおすすめされていたのです。なぜ?
その昔は苦手だったんですよ。どこがって言えないけど、なんか。
今見たら……けっこう感動しました。
忘年会シーズンですね。
昨日はひさしぶりに学生の頃の仲間で集まりました。
みんな、もう20年以上昔のことを、ここ数年のことよりもよく覚えているんですよね。
それだけ多感だったのでしょう。
各々環境は変わっているんだろうけど、あの頃と変わらず接することができるのも、この仲間ならでは。
付き合いが古いからこそのストレートな意見ももらいました。
このところあまり付き合いが良いとは言えない自分ですが、
みんなの活躍を聞くと自分も負けてられないと思います。
がんばります〜〜。


また先日、スクールの工事の進捗を見てきました。
だいぶ進んでおります。
レッスンルームはおよそ出来ており、カウンターなども作られていました。
あと2週間もせずに引き渡しです。
ドキドキワクワクです。
そろそろ楽器や設備などもそろえていかなければ。

上手くなくても音楽は楽しめます。
それでも、やるからには上達していきたい、と考えることは当然かもしれませんね。
これは他人からの評価と関係なく、習得していくこと自体に喜びがあるからだと思います。
そんなわけで、
「上手くならないといけない」
「上手くないと他人に聴かせてはいけない」
という刷り込みに対しては、そんなことはない!と、強調して念を押しつつ、
上達について考えてみたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
前回の補足です。
ちなみに、記憶というのは寝ている間に定着するらしいです。
ですので、もし毎日4分の練習や復習をするのであれば、なるべく寝る直前が良いでしょう。
ただ、これは私が実際に検証したわけではないので、どなたか「寝る前ちょっと学習」を実践して成果報告してください。笑
少なくとも、それがルーティン化すること自体が良いことだと思いますね。
あともう1つ、1回の練習(復習)の時間というか量ですが、これは最初は少なくしておいた方が良いと思います。
新たに入れる情報の量を抑えるという意味で。
やはり、詰め込みすぎると、記憶の維持リハーサルによって短期記憶から長期記憶に情報が送られる量を、新たに入ってくる短期記憶の量が上回ってしまい、定着せずに捨てられて(消えて)しまう情報が出てきます。
これではもったいないですね。
要は、インプットとメモライズは同時にはできないということです。
インプットとメモライズのバランスを取らなければならないのですね。
そういう意味では、バランスを取るために今日はインプットはお休みする、といった調整はアリだと思います。
それと、気負いすぎると長続きしないということもありますね。いわゆる三日坊主です。
じつは私自身、やるぞ!と意気込むほどに続かない奴でして……。半年続けば良い方という……。
逆に、自分でそんな意気込み確認なんかしてない、「なんとなく」くらいのことのほうが長く続いたりします。
ということで、坊主頭だった頃の私を貼っておきます。
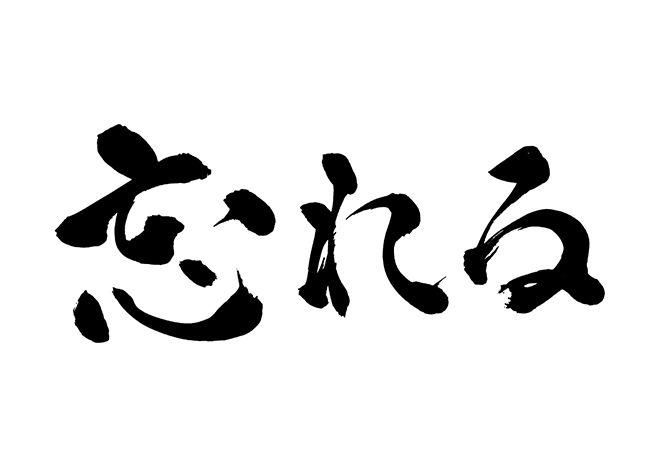
上手くなくても音楽は楽しめます。
それでも、やるからには上達していきたい、と考えることは当然かもしれませんね。
これは他人からの評価と関係なく、習得していくこと自体に喜びがあるからだと思います。
そんなわけで、
「上手くならないといけない」
「上手くないと他人に聴かせてはいけない」
という刷り込みに対しては、そんなことはない!と、強調して念を押しつつ、
上達について考えてみたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これもよく言われることですが、「短い時間でもいいから毎日練習した方が良い」です。
たとえば、月に1回、2時間(120分)の練習をするより、毎日4分(計120分/月)の練習をした方が良いです。
これは人間の記憶に関係があります。
人間は忘れていく生き物ですね。むしろ忘れることで、我々は正常に生きてられるのだそうです。
しかしながら、せっかく覚えたことまで忘れていってしまうのはもどかしいですね……。
それをしょうがないと言っていては話が終わってしまうので、忘れたくないことを忘れないようにするにはどうしたらいいか考えてみましょう。
記憶には大きく2つ、短期記憶と長期記憶というものがあります。
これらがどういうものかというと言葉のとおりなんですが、新しいことを覚えようとすると、それはいったん短期記憶として覚えられます。
レッスンのときに講師の言った内容を聞きながら理解したという段階では、それは短期記憶ということになります。で、悲しいことに、この短期記憶はものすごい勢いで忘れ去られていきます。20分後には42%を、1時間後には56%を、1日後には74%を忘れてしまいます。そんな自覚ないですよね……でも、そうらしいんですよ。
そこで、記憶の維持リハーサルというのをしていくと、短期記憶の情報が長期記憶に変わっていくのです。長期記憶は脳にしっかりしまわれて、消えることはないとされています。(それでも長い間放置しておくと、呼び出すことが困難になってくるようですが。)
ということで記憶の維持リハーサルが大切なんですが、これは簡単にいえば、忘れてしまう前に思い出して記憶をフレッシュな状態に保つということです。
月に1回、どんなに長い時間練習をしても、そこで得たものはあっという間に消えて無くなってしまいます。
まずは少ない情報を、毎日復習することで確実に定着させ、さらに情報を少しづつ増やしていくのが効率が良いということになります。
「一歩進んで二歩下がる」ようなことがないよう、0.5歩づつでも下がることなく進んで行きたいですね。